|
 日本精糖跡 日本精糖跡
1949年(昭和24)川辺町に創業。2001年(平成13)生産終了、フジ製糖との合併により閉鎖。跡地はコーナン付近。 |
|
 古河電池跡 古河電池跡
1940年(昭和25)古河電気工業(株)の電池制作部門が分離独立、星川に創業、1986年(昭和61)にいわき市、今市市に工場移転。本社は工場跡地の星川駅前に所在。跡地はいなげや、星川中央公園、高層マンション付近。
<追記2024.2.1>JAXAが開発したSLIM<小型無人探査機>が1月20日に初めて月面着陸に成功した。SLIMには古河電池が開発・製造した宇宙用リチウムイオン電池が搭載されているという。無人探査機を月面着陸させたのは旧ソ連、米国、中国、インドに次ぐ5カ国目となる快挙を成し遂げた。 |
|
 富士瓦斯紡績跡 富士瓦斯紡績跡
1903年(明治36)川辺町に創業。1943年(昭和18)に撤収。最盛期には従業員6000名を超える世界最大級の生産量を誇る製糸工場として稼働。「富士絹」を着こなすことは、当時の男性のおしゃれの代名詞。表門から延びる現在の天王町商店街(通称・シルクロード天王町)は企業門前町として賑わった。跡地は区役所、消防署、川辺公園、イオン天王町店(2020年の営業再開を目指し建物を取り壊し建て替え中)付近。 |
|
 保土谷曹達(保土谷化学)跡 保土谷曹達(保土谷化学)跡
1916年(大正5)帷子町に創業。1973年(昭和48)に当地から撤収し郡山に移転。日本初の電解法苛性ソーダーメーカー。跡地は公団天王町団地付近。 |
|
 鯉のぼり 鯉のぼり
常盤橋付近で、こどもの日を前に100匹余りの鯉のぼりが川の上を空高く泳いでいる。40年近く前から毎年掲揚しているという。今年は(2020年)新型コロナの影響で、人出は少なかったが例年に負けずに空に泳いでいた。 |
|
 古町橋 古町橋
帷子川の流路は現在の古町橋の手前辺りから南に大きく蛇行して、天王町駅の南側を流れていた。これが氾濫のもとで流路を変更したことにより、旧古町橋から約120メートル北側に現在の古町橋が架設された。 |
|
 旧古町橋跡 旧古町橋跡
江戸時代初期の東海道(古東海道)が帷子川に架かる旧古町橋。古代の東海道のルートではこの古川橋で帷子川を渡った。 |
|
 帷子橋のモニュメント 帷子橋のモニュメント
1964年(昭和39)の改修以前に架かっていた帷子橋(新町橋とも云う)が現在の天王町駅駅前公園にモニュメントとして復元されている。新しい帷子橋は旧川筋の北側に付け替えられ、下流の流れはすっきりしたものとなった。この帷子橋(新町橋)は北斎、広重の絵となり保土谷宿の象徴であった。 |
|
 南北石油跡 南北石油跡
1905年(明治38)に創業。日本石油の前身で、石油アスファルト製造の草分け。跡地は西久保町公園。 |
|
 東洋電機製造跡 東洋電機製造跡
1919年(大正8)西久保町に創業。我が国初の鉄道車両電気機器メーカー。現在の生産拠点は横浜市金沢区、滋賀竜王町の二個所。車両を移動させる引込線が保土ヶ谷駅に直結して今も残されている。公団西久保町公園ハイツ付近。 |
|
 日本金属工業跡 日本金属工業跡
1932年(昭和7)西久保町に創業。その後、碧南市に移転。日本で最初にステンレス鋼の国産化に成功。記念として、「ステンレス鋼発祥の地」の碑がある。公団西久保町公園ハイツ付近。 |
|
 ひろた屋 ひろた屋
帷子川の捺染工場であった元祖ひろた屋から暖簾分けし、大正11年に染物を行う紺屋として創業。現在はまちかど博物館として運営。岩間町。 |
|
 大日本麦酒(日本碍子)跡 大日本麦酒(日本碍子)跡
元はこの地で、湧水を活用した「東京ビール」をブランドとする東京麦酒を大日本麦酒(現サッポロビール)が買収して、1907年(明治40)神戸に創業。ビールと清涼飲料水を製造したことに始まる。隣地に1916年(大正5)日本碍子が進出し、合併、分離を繰り返し、大日本麦酒から独立。日本碍子は1985年(昭和60)に閉鎖。跡地は横浜ビジネスパーク(YBP)、保土谷スポーツセンター、保土ヶ谷小学校付近。 |
|
 ベリーニの丘 ベリーニの丘
YBP広場は多彩なアート作品で構成されているが、その一つ、イタリアの建築家、デザイナーのマリオ・ベリーニの水のホール。 |
|
 ビール坂 ビール坂
神戸の交差点から桜ヶ丘の月見台まで延びる約400mの急坂。近くに湧水を活用した麦酒工場があったことから「ビール坂」という名が付けられたという。 |
<歴史と自然を探し中・上流域へ>
 日本カーリット跡 日本カーリット跡
1919年(大正8)「明治のセメント王」と言われた浅野総一郎氏がスエーデン・カーリット社からカーリット爆薬の製造・販売権を取得し、仏向町に創業した火薬類を製造する民間会社。火薬庫に繋がるレンガ造りのトンネルや土塁、トロッコのレールなどの遺構が残っている。1995年(平成7)火薬類の製造拠点を群馬赤城工場に移転。跡地はたちばなの丘公園、サンシテイ横浜。 |
|
 たちばな公園 たちばな公園
公園一帯は火薬工場の緩衝林としての雑木林や谷戸が残されている。 |
|
 トロッコ用のレール跡 トロッコ用のレール跡
土塁に囲まれた工室跡への出入り口として使用されたトンネル内のトロッコのレールが残っている。 |
|
 工室跡へのトンネル 工室跡へのトンネル
土塁に囲まれた各工室跡への出入り口として使用されたトンネルが用途別に8カ所保存されている。 |
|
 万年塀 万年塀
火薬類が製造される危険区域のため、コンクリート塀が設けられ立ち入りが禁止されていた。現在も一部が保存されている。 |
 坂本捺染 坂本捺染
1953年(昭和28)創業の横浜スカーフの染色を取り扱っている坂本町に所在する捺染工場。そもそも捺染とは布に柄を染める技術の総称で、横浜の地場産業の一つ、横浜スカーフの製造・捺染業者が帷子川中流域の鶴ヶ峰から西谷、星川間に立地していた。周辺にはkkモリヤマ(跡地に満天の湯を経営)や大木捺染kkなど多くの工場が建ち並び、川の水を赤や青で染めていたという。 |
|
 ほどがや☆元気村(西谷の田んぼ) ほどがや☆元気村(西谷の田んぼ)
保土ヶ谷区西部地区を中心に広がっていた田園風景は昭和40年頃より減少の一途を辿る中で、帷子川沿いに唯一残る水田600坪の内、100坪ほどが子供たちの稲作体験の場として提供され、米作りや畑作業に取り組んでいる。 |
|
 田園風景 田園風景
6月頃に米の苗を植え、10月頃には稲は順調に育ち、稲刈り作業を終えると、脱穀・籾摺りと乾燥・精米などの作業を経て食卓に届けられる。 |
|
 用賀下橋の魚道 用賀下橋の魚道
アユにとって堰や段差が遡上の妨げになるので、遡上をスムーズにするため、魚道が作られている。こうした装置によって、かなり上流までアユの魚影が見られるという。 |
|
 川底から露出している泥岩 川底から露出している泥岩
この川はかつてはしばしば氾濫を繰り返していたので、川幅を広げ、河床を掘り下げる大規模な河川工事が行われた。その結果、鶴ヶ峰の用賀下橋付近の川底にも黄鉄鉱などの酸化鉱物を含む地層が露出しているところが見られる。この地層は浸食されやすいのでコンクリートで補強されているが、かつてはこれを土台にして染物の水洗いが盛んに行なわれていたと云う。 |
<中流域の鶴ヶ峰には、重忠ゆかりの史跡や伝承が数多く残っているので、これを機会に重忠公ゆかりの地にも足をのばしている> |
|
 首洗い井戸・鎧の渡し 首洗い井戸・鎧の渡し
元久2年(1205)、二俣川の地で最期を遂げた重忠の首を洗い清めたと云われる井戸跡。右に見えるプロムナードは帷子川跡地を埋め立て整備した道で、鎌倉時代の武士は鎧を頭上に持ち上げ、川を越えたことから鎧の渡しと呼ばれた。 |
|
 首 塚 首 塚
愛甲三郎季隆(矢の名手)の矢で射たれた重忠の首が、やや小高いところに葬られている。その側には塔と地蔵尊が建てられ、霊を慰めている。 |
|
 畠山重忠公碑・さかさ矢竹 畠山重忠公碑・さかさ矢竹
畠山重忠公没後750年を記念して埼玉県川本町(現・深谷市)と鶴ヶ峰の有志によって建立された。手前の竹は、さかさ矢竹で、重忠公が矢にあたった時に「我が心正しかれば、この矢に枝葉を生じ繁茂せよ」と云い、地面に突き立てた二本の矢が毎年二本ずつ増え、茂り続けたと云われている。 |
|
 六ツ塚(薬王寺) 六ツ塚(薬王寺)
境内には討ち死にした畠山重忠をはじめ、一族郎党の百三十四騎の屍を埋めたとされる六つの土饅頭(写真は重忠公の塚と言う)があったと伝わる。 |
|
 薬王寺・地蔵尊 薬王寺・地蔵尊
塚の周辺には、地蔵尊が建てられ重忠をはじめ一族郎党の霊を慰めている。薬王寺には重忠の霊が祀られ、霊堂になっている。 |
|
 駕籠塚 駕籠塚
重忠公の内室「菊の前」は合戦の知らせを受け、急ぎ鶴ヶ峰に駆けつけたが、その寸前で重忠の悲報を聞き、この地で重忠の後を追って自害し、駕籠ごと埋葬されたと伝えられている。 |
|
 畠山重忠公遺烈碑 畠山重忠公遺烈碑
元久2年(1205)6月22日、「鎌倉に異変有り」との連絡を受けた畠山重忠は134騎で、「菅谷の舘」を出陣し、戦場となった武蔵国二俣川(現在の横浜市旭区)で、北条軍三万騎余りの軍勢と奮戦の後遂に当地で戦死した。この地は元とは「牧が原」と云われていたが、この辺りに数万騎余りの陣を構えたことから「万騎が原」になったと伝えられているが、現在では合戦の遺構は残っていない。 |
|
 矢畑・腰し巻き 矢畑・腰し巻き
北条勢が放った矢がこの辺り一面無数に落下し、矢の畑のようになったと言うことから矢畑と呼ばれている。またこの辺りで取り囲まれたと言うことで、腰巻きという。 |
|
 清来寺 清来寺
古くは厚木にあったが、寛永年間にこの地に移された。19代住職が畠山重忠の武勇を称えるため近在の人々に呼びかけ編纂された「夏野の露」という絵巻が伝えられている。境内には鎌倉時代に伝令として使っていた鐘があったという鐘楼塚がある。鐘楼塚は畠山重忠が所持していた観音像が埋められており観音塚とも呼ばれている。 |
|
 旭図書館 旭図書館
横浜市旭区ゆかりの武将 畠山重忠を紹介するパネル展が2023年1月11日から3月31日まで当図書館で開催されている。清来寺は訪ねているので「夏野の露」の歌集、絵巻は興味深く見学した。
左下のパネルは曽我物語 巻八に記載された、 曾我兄弟との富士野の巻き狩りの場面で、重忠を情けを知り教養のある武士として登場させていると云う。「英雄三十六歌撰 畠山重忠(馬の博物館蔵)より」 |
|
 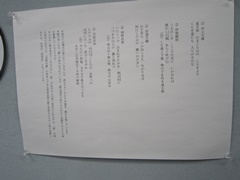 「夏野の露」絵巻、歌集 「夏野の露」絵巻、歌集
鶴ヶ峰で非業の死を遂げた重忠公の武勇を称えるために1852年(嘉永5)に、19代住職が呼びかけた地域の有力者により制作された歌集、絵巻をまとめたもの。右は原文 の一部を明朝体に直したもので、重忠の人柄を偲ぶ歌が掲示されている。 |
|
 鶴ヶ峰周辺の俯瞰図 鶴ヶ峰周辺の俯瞰図
当時の鶴ヶ峰周辺の様子が俯瞰図として描かれている部分。 |